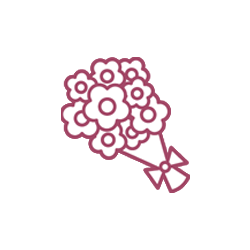【お正月】仏壇のお供え物に「のし」は必要? おすすめのお供え物や金額相場も解説

※本ページにはプロモーションが含まれています
お正月に仏壇へお供え物をする家庭も少なくないでしょう。
お供え物にはのしが必要なのか、そもそもお正月にお供え物をするのが正しいのか、マナーも含めて気になりますよね。
今回は、お正月の仏壇へのお供え物について解説します。
お供え物にふさわしいおすすめの商品も紹介するので、お正月に間に合うようしっかり準備しておきましょう。
お正月は仏壇にお供え物をする?
お正月に仏壇にお供え物をするかは、各家庭の考えや地方の風習によって異なります。
もともと、お正月はお盆と同様、先祖供養の行事とされていました。
先祖供養の風習が残る地域では、お正月に仏壇にお供え物をする家庭もあるでしょう。
一般的なお正月を過ごす地域では、手土産を持参すれば問題ありません。
頂きものを仏壇にお供えしてから食べる習慣の家庭も多く、いずれにしてもお供え物と同様の結果となることもあるでしょう。
お供え物には「のし」をつける?
仏壇へのお供え物には、のしがない掛け紙をつけましょう。
黄白もしくは黒白の結び切りの水引を使用し、上段に「御供」や「御仏前」と記載します。
親戚が多く集まる場合、誰が渡したかわかるよう、水引の下段にはフルネームを入れましょう。
お正月に仏壇にお供え物をする習慣がなく、手土産として持参するときの水引は、紅白5本の蝶結びを選びます。
のし紙の水引の上段は「御年賀」とし、三が日の間に渡すのがマナーです。
お供え物の金額相場
お正月のお供え物の金額相場は、3000円~5000円です。
お金を包む場合、お菓子などの手土産を持参する場合、いずれにしても3000円~5000円が相場となります。
あまり高価なお菓子を持参すると、かえって相手に気を遣わせてしまいます。
親戚一同、気持ちを楽にしてゆっくりとお正月を過ごすためにも、一般的な範囲内の手土産を選びましょう。
喪中の場合はどうするか
喪中の際、四十九日が明けるまでは慶事を控えるため、お正月飾りや年賀状の送付などを行わないのが一般的です。
しかし、喪中の場合でも、仏壇へお供え物をしてはいけないというわけではありません。
喪中の家庭へのお正月のお供え物は、1月1日~7日の松の内が明けた「寒中」に贈りましょう。
のし紙の表書きは「寒中見舞い」とするのがマナーです。
お供え物はお菓子など個包装タイプがおすすめ
お正月に贈るお供え物は、お菓子や飲み物、果物などが定番です。
特に、切り分けたり皿を用意したりする必要のない、便利な個包装タイプのお菓子が喜ばれます。
仏壇にお供えした後、個包装のお菓子や飲み物だと親戚が集まった場面でも分けやすいのがポイント。
特に、お菓子やジュースは、子どものおやつとしても重宝するお供え物です。
仏壇のお供え物としてNGなもの
仏壇のお供え物として、NGとされるものもあるため注意しましょう。
例えば、殺生を連想させる肉や魚は、お供え物としてふさわしくありません。
また、賞味期限の短い食べ物やアルコール類は、もらって困る可能性があるため避けるのがベター。
喪中の際は、昆布や鯛、かつおなど、慶事をイメージさせるおめでたいものも控えましょう。
【お正月】仏壇のお供え物おすすめ9選
ここからは、お正月の仏壇のお供え物としてふさわしいアイテムを紹介します。
のしもしっかり用意して、すてきなお正月ギフトを贈りましょう。
味噌煎餅本舗 井之廣 抹茶入り 味噌煎餅 13袋入り お供え物
大彌 七転八起5個 みなくち5個 しるべ5個
大彌 和菓子 「みのり」 お供え
中島大祥堂 黒わらび餅 6号 KWA-10
鼓月 プレミアム千寿せんべい 24枚入
富久屋 花園 30個入
銀座千疋屋 銀座ひとくちフルーツゼリー 28個
舞玉
石村萬盛堂 焼菓子詰合せ 欧集花 S
まとめ
今回は、お正月の仏壇へのお供え物について解説しました。
お正月に仏壇へお供え物をするかどうかは、各家庭や地域によって異なります。
お供え物が必要な場合は、のし紙をかけて持参しましょう。
親戚同士で分けやすいよう、個包装のお菓子や飲み物などがおすすめです。
当記事で紹介した商品も参考に、すてきな1年の始まりとなるようなお供え物・手土産を選びましょう。
※本記事では送料を想定しない価格で商品を選定しています。
※各商品の説明文は各ECサイトを参考に作成しています。
※商品は掲載時点の情報を参考にしています。最新の情報は各ECサイトをご参照ください。